並ぶことの心理学:並ぶことが意思決定に与える影響
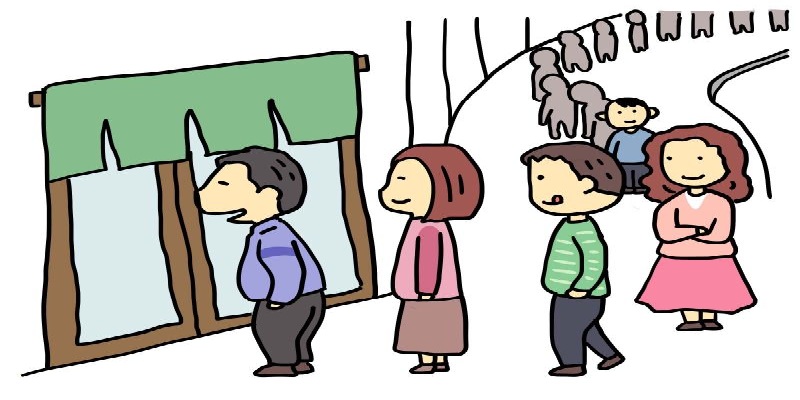
みなさんは行列に並ぶのは好きでしょうか?飲食店やイベントなどで行列ができているのを見ると、何だろうと興味がそそられますよね。数が限られている商品の販売時や、人気の飲食店などでは何時間も並んで待つ場合があります。行列に並んで自分の番が来た時に品物の購入やメニューやサービス等の選択を行いますが、研究によると、行列に並んでいた時の周囲の状況が、その際の購入や選択などの意思決定に大きく影響しているようです。本コラムでは、行列に並ぶことが人の行動や気分を変えてしまう事例を紹介します。
並ぶと買いすぎる?
ある研究では、並ぶことが商品購入時の意思決定に影響するかを調べるために、実際のカフェでお客がカウンターに並んでいる時間と、その人の支払い額の間の関係を調べました(1)。その結果、並んでいる時間が長いほど、支払い額も増加する傾向が見られました。時間帯や注文時に後ろに並んでいる人数、同行人数などの影響を考慮しても、この傾向は見られました。並んでいる時間が多いと、ついつい多く購入してしまう可能性があることをこの結果は示しています。
このようなことが起こる原因は、実際の現場での調査ということもあり、この結果からは説明するのが難しいと考えられます。そのため著者らは、実験室でよりコントロールされた実験を実施しました。
この実験では、参加者は動画を見て映っている人物を評価するというものでした。実験時に対象の動画をダウンロードするのですが、ダウンロードにかかる時間が短い参加者グループと長い参加者グループがありました。参加者は、ダウンロードした複数の動画の中から何本の動画を評価するか選べるのですが、ダウンロードに時間がよりかかったグループの方が、多くの動画を選択しました。また、ダウンロードに時間がかかったグループの方がダウンロードが完了するのを待つのにイライラしていました。このように、長く待つ方が不快にも関わらず、より多くのものを選択するような傾向があるようです。不快な気分が選択を増加するのは、ネガティブな気分を解消しようとして、より多くのものを得ようとしているための可能性がありますが、詳細は不明です。しかし、このようなメカニズムが、待つことが消費を助長する背後にあるのかもしれません。
さらに、ただ待つ時間の長さだけが重要ではなく、待たされる理由も重要のようです。上記の動画のダウンロードの実験で、参加者はダウンロードするのに待たされる理由が、他の人も動画をダウンロードしようと同時にサーバーにアクセスしているためと教えられた場合と、単にサーバーが関係のないタスクも同時に行っているためと教えられた場合がありました。結果は、前者の他人の同時アクセスによる遅延の場合、長く待たされるとより多くの動画を視聴する傾向がありましたが、後者の無関係タスクによる遅延の場合は、逆の傾向になりました。この結果から、参加者は待たされるのはその動画が他の人からも人気があり、動画に価値があると考えた結果、より多くの動画を選択した可能性があります。
同じように、オンラインショップを模した実験で、店のウェブサイトをロードするのに時間がかかるのは他の人もアクセスしているためと言われた場合と、単に関係のないシステム負荷のためと言われた場合では、前者の同時アクセスの状況で待つ時間が長い場合は短い場合より、多くの商品を選択する傾向がありました。単なるシステム負荷と教えられた場合は、待つ時間による商品の選択数への影響はありませんでした。この結果も、待たされる理由が、多くの人が興味を持っているからと考えた結果、価値が高まり自分の選択行動に影響した可能性を示唆します。
このように、待つことの不快さや他者の存在による価値向上が、待つことにより消費を増加させている可能性があります。さらに、ただ待つだけでなく、待たされる理由がその後の意思決定に重要であることも示されています。お店などで売り上げを伸ばしたい時は、適度に行列ができる仕組みを作っておくといいかもしれません。ただしその際は、レジ対応の効率の悪さなど、人気とは関係のない理由で待たされているとお客さんに認識されないようにすることが必要そうです。
並ぶの途中でやめる?後ろに結構人いるけど
行列に並ぶのを途中で諦めて行列から離脱したことがある人もいると思います。行列に並んでいる時の気持ちや行列に並ぶのをやめる決断は、当然自分の前に並んでいる人数が大きく影響します。自分の前に並ぶ人が多いほど自分の番が来るまでより時間がかかることが予想されるので、不快になりますし、並ぶのを止めて離脱する決断をする可能性が高くなります。しかし、研究によると、自分の後ろに並ぶ人数も、並んでいる時の気分や離脱の決断に影響していることが示されています(2)。自分の後ろに並んでいる人数は、自分の番が来るまでの時間には全く影響しませんが、感情や決断に影響しているのは不思議ですね。
例えば、お昼休憩時の銀行のATMは、多くの人が利用しようとするため行列ができます。ある都市のATMでお昼時に観察を行うと、ATMの行列に並んだ人がその列から離脱するかどうかは、その人の後ろに並んでいる人数の影響を受け、後ろに並んでいる人数が多いほど列から離脱する可能性が低くなっていました。
さらに仮想的なシナリオを用いた調査では、参加者に郵便局で重要な書類を送付するために列に並んでいるシーンを思い浮かべてもらいました。参加者は列に並んでいる時の気分や、追加の料金を払えば列から離脱して即座に書類を送付できるサービスがあるときにそのサービスを利用するかを回答しました。予想どおり自分の前に並んでいる人数が多いほどポジティブ気分は減少し、ネガティブ気分は上昇していました。面白いのは、自分の後ろに並んでいる人数が多いほどポジティブ気分が上昇し、ネガティブ気分は減少していました。さらに、列から離脱すると判断した人数も、後ろに並んでいる人数が増えると減少する傾向がありました。後ろに並んでいる人数は、自分の番が回ってくるまでの時間には影響しないにも関わらず、並び列から離れるかの決断や気分に影響しているようです。
さらに、この研究では、後ろに並ぶ人がどのように自分に影響しているのかさらに詳しく検討しています。お店や銀行の窓口などで自分の番を待つ時、行列を作ってその列に並んで自分の番を待つタイプと、最初に番号が記載された紙を受けとり、好きな場所で待機し自分の番号が呼ばれるまで待つタイプがあります。行列に並ぶタイプの方が、番号呼び出しタイプより自分の後ろに並んでいる人数が把握しやすいと考えられます。番号呼び出しタイプは、自分の後ろに何人いるかは後から来た人を観察して数える必要があります。このような2つのタイプの行列待機の仮想的な状況を参加者に想定してもらい、行列を離脱するかどうかを尋ねた場合、どちらも自分の後ろに並ぶ人数が多いほど離脱する可能性は低くなりました。さらに行列に並ぶタイプの待機のほうが、後ろに並ぶ人数が多い時、行列から離脱する可能性はより低くなっていました。
加えて、ポジティブ気分やネガティブ気分を聞くと、後ろに並ぶ人数が多いほどポジティブ気分は上昇し、ネガティブ気分は低下していました。気分もまた並ぶタイプによって差があり、後ろに並ぶ人数が多い時、行列に並ぶタイプの方がよりポジティブ気分が高く、ネガティブ気分がより低くなっていました。
後ろに並ぶ人数が多いと、列から離脱する可能性が低くなること、さらにポジティブ気分が高くなり、ネガティブ気分も低くなるようです。後ろに並ぶ人数が多いと、自分の後ろに並んでいる人々と比較して自分の優位性を認識して、気分が良くなり、それが離脱を防いでいるのかもしれません。またこの傾向は行列に並ぶような明確に後ろの人数が把握できるような状況の方が強く現れていることから、自分の後ろにならんでいる人々が自分の意思決定や気分に影響するという仮説を支持しています。
さらに人の性格もこの現象に影響しているようです。人の性格には、自分と他人を比較する傾向が強い人と弱い人がいます。ここまでの結果で自分と自分より後ろに並んでいる人の比較が重要である場合、後ろに並ぶ人数の影響は、自分と他人を比較する傾向が強い人の方が、弱い人に比べて顕著にでることが予想されます。実際に、アンケートで取得した他人と比較する傾向が強い人は弱い人に比べて、後ろに並ぶ人数が多いと列から離脱する可能性の低下、ポジティブ気分の上昇やネガティブ気分の下降の傾向がより大きく現れていました。
自分の後ろに並んでいる人数は、行列に並んでいる時の自分の番がくるまでの時間には影響しませんが、人数が多くなると、自分と後ろに並んでいる人々を比較しその結果、列を離れるかの決断に影響しているようです。
ある商品やサービスを提供する際に行列ができた場合、販売者としては売上を伸ばすために、できるだけ並んでいる人に離脱してほしくないと考えるものです。そのためには並んでいる人に自分の後ろに何人並んでいるかが可視化されると離脱する可能性は低くなると考えられます。ただし、行列が長いとそもそも並ばない選択をする人も増えると考えられるので適度に行列が可視化されるのが必要そうです。
気になる他人の行動と視線
あるサービス(セルフサービスや店舗で最新式スマホを試すなど)の行列に並んでいて自分の番が来た時に、どれだけ自分がそのサービスに時間を使うのかも行列の状況に依存するようです(3)。
コンピューター上の仮想的な環境でそのようなサービスのための行列に並ぶのを模倣した実験では、自分の前に並んでいる人がそのサービスに使う時間が長いほど、自分の番がきたときにサービスに使う時間も長くなる傾向がありました。また、自分の後ろに並んでいる人が多いと、少ない場合に比べて、自分がサービスに使う時間が減少する傾向がありました。
これは、社会的な相互関係(前の人が短かったら自分も短く、長かったら自分も長く)や社会的プレッシャーが自分のサービス利用時間の意思決定に影響していることを示しています。このようなメカニズムは、自分の満足度を高めつつもスムーズに行列が進むためには必要なのかもしれません。
まとめ
このように行列に並んでいるときの様々な状況が、列に並んでいる時や自分の番がきたときの意思決定や気分に大きく影響しています。ここで述べた要因は一部で、実際の行列では他にも様々な要因が自分に影響を及ぼしていると考えられます。
行列に並ぶことの影響を知ることは、自分の番が来た時により良い選択や気分を良く保つために有益であると考えられます。例えば、最初は大してお金を使うつもりはなかったのに、並んでいるうちにあれもこれも欲しくなり結局たくさん買ってしまうという経験をした人は多いのではないでしょうか。行列に並ぶことの影響を知ることで、そのような無駄遣いをしてしまうのを防げるようになるかもしれません。ただ、推し活などでは長時間行列に並んで散財すること自体を楽しんでいる人もいるようですが(!)、後になって振り返るとお金では買えない、いい思い出になっている可能性がありますね。
センタンでは、脳波や心拍、皮膚電気活動などの生体情報の計測・解析から、ヒトの状態や影響などを深く知るサポートを行っています。研究・開発支援(受託研究)や生体データの利活用支援など様々な課題解決のサポート実績がございますので、興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
引用文献
- Munichor, N., & Cooke, A. D. (2022). Hate the wait? How social inferences can cause customers who wait longer to buy more. Frontiers in Psychology, 13, 990671.
- Zhou, R., & Soman, D. (2003). Looking back: Exploring the psychology of queuing and the effect of the number of people behind. Journal of Consumer Research, 29(4), 517-530.
- Kim, H., Lee, Y. S., & Park, K. S. (2018). The psychology of queuing for self-service: Reciprocity and social pressure. Administrative Sciences, 8(4), 75.
● 引用・転載について
- 当コンテンツの著作権は、株式会社センタンに帰属します。
- 引用・転載の可否は内容によりますので、こちらまで、引用・転載範囲、用途・目的、掲載メディアをご連絡ください。追って担当者よりご連絡いたします。
● 免責事項
- 当コンテンツは、正確な情報を提供するよう努めておりますが、掲載された情報の正確性・有用性・完全性その他に対して保証するものではありません。万一、コンテンツのご利用により何らかの損害が発生した場合であっても、当社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。
- 当社は、予告なしに、コンテンツやURLの変更または削除することがあり、また、本サイトの運営を中断または中止することがあります。
