生成AIと拡張する脳
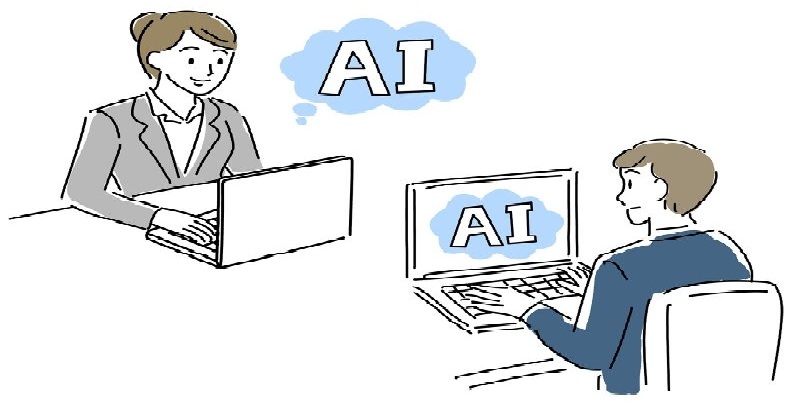
出張前夜に企画書の骨子を整える。まずは自分で論点を書き出し、途中で生成AIに「代替案を3つ」と頼む——数分で視点が広がり、その後は自分の言葉で磨き込む。いま多くの人が、このような“人×AI”の往復運動で仕事を進め始めています。私たちの脳と心は、この新しい相棒をどう使いこなしていけばよいのでしょうか?このコラムでは、最新研究の知見と、これまでのコラムで扱ってきた創造性、好奇心、ワークエンゲージメントなどの視点をつなぎ、企業実務にも効く使い方の工夫を提案します。
生成AIはいま何を変えているのか
コンサルティング現場の大規模実験では、生成AIを使ったグループはタスク完了数が平均12.2%増え、所要時間が平均25.1%短縮し、特に「アイデア創出型」の課題解決で品質向上が確認されました(1)。一方で、厳密な事実検証や定量分析の精度が問われる課題では、AIへの過信が誤りに結びつくことも指摘されており、生成AIの「まだらな技術的境界(Jagged Technological Frontier)」も示されています。ソフトウェア開発でも、生成AIによるコード補完支援ツールを使ったグループは、使っていないグループと比較してタスクを約56%早く終えるなど生産性向上が再現されています(2)。ただし、速度の向上がそのまま品質や安全性の向上を保証するわけではない点に注意が必要です。
こうした生成AIの得手不得手の境界を読み解く鍵は、人間側の認知特性です(3,4)。自動化バイアス(生成AIの出力を過度に信じてしまう傾向)や初期印象による過信・忌避(生成AIの出力が当たった/外れた経験の影響)は、意思決定の質を大きく左右します。
生成AIを「拡張する脳」としてどのように使っていけばいいのか
メモ帳や検索エンジンが私たちの「外部の記憶」になるように、生成AIは「思考」の外付け装置として機能します。生成AIを使うことによる、私たちの思考の広がりは「脳の拡張」として捉えられます。道具や外部媒体に処理を委ねる「認知オフローディング」は作業の負荷を下げますが、やり方次第では「覚えなくなる」「考えなくなる」という副作用も起こります(5)。したがって何を外に出し、何を自分の頭に残すかの設計が重要なのです。人間のチームにおいては「これについては、あの人が詳しい」といった「分担された記憶」が働きます。生成AIにおいても、「何を得意とする共同作業者か」というように考え、役割分担を明確にすると、人間個人の持つ脳の資源を、例えば検証や判断などに集中させることができます。
例えば、創造性のパフォーマンスを高めたい場面について考えてみましょう。創造性研究の最新のレビュー(6)では、生成AIが学習や日常の小さな創造から専門的創作までにおいて広く支援できることが示されています。創造性は、多くの選択肢やアイデアを生み出す発散と複数のアイデアから最適な解決策を選び出す収束の往復で生まれます(詳細は、コラム「創造性と脳:日常に潜むアイデアの源泉」をご覧ください)。発散段階では、生成AIに連想・類推・反例を大量に出してもらい、収束段階では人間が選択・統合・表現を担うといったような非対称の役割分担が有効です。発散段階で生成AIが出した大量のアイデアに触れ、自分の知識とのギャップを脳が察知するだけで、脳の報酬系の活動が高まり、好奇心へのドライブがかかります(コラム「好奇心:学びと成長を加速させる脳の仕組み」)。その後の収束段階も生成AIに任せることは技術的には可能ですが、人間側のワークエンゲージメントを高めるためにも、好奇心へのドライブが高まった上で、アイデアの検証と最終判断は人間自身が担うという使い方が肝心です(コラム「ワークエンゲージメント:いきいきわくわく働いていますか?」)。
現場で効く3つの工夫
ここまで見てきたように、生成AIには得手不得手のまだらな境界がありますし、私たち人間の認知オフローディング問題もあります。また、人間が生成AIを過信したり、逆に一度の間違いだけで不信感を抱いたりする傾向も考慮した使い方が必要です。では、現場では生成AIをどう活かせばよいのでしょうか?ここでは3つの工夫を紹介します。
1つ目は、生成AIと人の「役割分担」を明確にし、先に分業を決めることです。まず、チームの主要タスクを1枚の「地図」に整理し、それぞれを生成AIファースト(発散・草案・言い換え・要約など)とヒューマンファースト(事実検証、数値の精査、再計算、倫理・法令の判断、最終合意形成など)に振り分けます。研究でも示されたように、生成AIが得意な領域と不得意な領域は入り混じっており、この「まだらな境界」を見極めることが大切です。チームでタスクごとに「生成AIに向く部分」「人が担うべき部分」といった地図を作っておくと、安心して使えます。
2つ目は、生成AIへの過信を避けるための「検証の仕組み」をプロンプトに埋め込むことです。人間が持つ自動化バイアスを弱めるには、生成AIに出すプロンプトの段階で反証と多様化を組み込みます。例えば「反対意見を3つ挙げよ」「この案が失敗する前提を列挙」「他部署の視点で言い換え」といったプロンプトを標準化すると、視野が広がり自動化バイアスを抑えることができます。
3つ目は、認知オフローディングの問題を考慮して、「効果と学び」を両立して評価することです。生成AIの導入効果を見る時には、業務時間の短縮やミスの減少といった業務指標を追うことが必要ですが、同時に、人が基礎的な知識を維持できているかも確認する必要があります。もし生成AIの導入でスピードは上がっても、社員が基本的な判断力を失ってしまえば、長期的なリスクになります。例えば、覚えないと正しく判断できなくなる基礎知識に関することは生成AIに分担させないなどの方針を明確にするとよいでしょう。また、月に一度は生成AIを使わずにタスクに取り組み、基本知識が保たれているかを点検することも有効です。
まとめ
生成AIは、発想を広げたり文章を整えたりする場面では強い力を発揮しますが、数値や事実の確認などは人間が担う必要があります。また、生成AIの答えを過信したり、逆に一度の誤りで信頼を失ったりするのも人間の特徴です。こうした特徴を理解した上で、役割分担を明確にし、反証を促す問いかけを組み込むことなどで、効果と学びの両方を見ていくことが大切です。生成AIを「拡張する脳」として位置づければ、単なる作業の効率化にとどまらず、人が本来注力すべき判断や創造の余地を広げることができます。スピードと品質を両立させるには、生成AIに任せる部分と人が責任を持つ部分の線引きを続けて調整することが欠かせません。小さな工夫の積み重ねが、生成AIとの健全な協働を実現し、個人やチームの力をさらに高めていくことにつながります。
センタンでは、脳波や心拍、皮膚電気活動などの生体情報の計測・解析から、ヒトの状態や影響などを深く知るサポートを行っています。研究・開発支援(受託研究)や生体データの利活用支援など様々な課題解決のサポート実績がございますので、興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
引用文献
- Dell’Acqua, F., McFowland III, E., Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K., Rajendran, S., … & Lakhani, K. R. (2023). Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of AI on knowledge worker productivity and quality. Harvard Business School Technology & Operations Mgt. Unit Working Paper, (24-013).
- Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., & Demirer, M. (2023). The impact of ai on developer productivity: Evidence from github copilot. arXiv preprint arXiv:2302.06590.
- Pop, V. L., Shrewsbury, A., & Durso, F. T. (2015). Individual differences in the calibration of trust in automation. Human factors, 57(4), 545-556.
- Logg, J. M., Minson, J. A., & Moore, D. A. (2019). Algorithm appreciation: People prefer algorithmic to human judgment. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 151, 90–103.
- Risko, E. F., & Gilbert, S. J. (2016). Cognitive offloading. Trends in cognitive sciences, 20(9), 676-688.
- Ivcevic, Z., & Grandinetti, M. (2024). Artificial intelligence as a tool for creativity. Journal of Creativity, 34(2), 100079.
● 引用・転載について
- 当コンテンツの著作権は、株式会社センタンに帰属します。
- 引用・転載の可否は内容によりますので、こちらまで、引用・転載範囲、用途・目的、掲載メディアをご連絡ください。追って担当者よりご連絡いたします。
● 免責事項
- 当コンテンツは、正確な情報を提供するよう努めておりますが、掲載された情報の正確性・有用性・完全性その他に対して保証するものではありません。万一、コンテンツのご利用により何らかの損害が発生した場合であっても、当社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。
- 当社は、予告なしに、コンテンツやURLの変更または削除することがあり、また、本サイトの運営を中断または中止することがあります。
